-
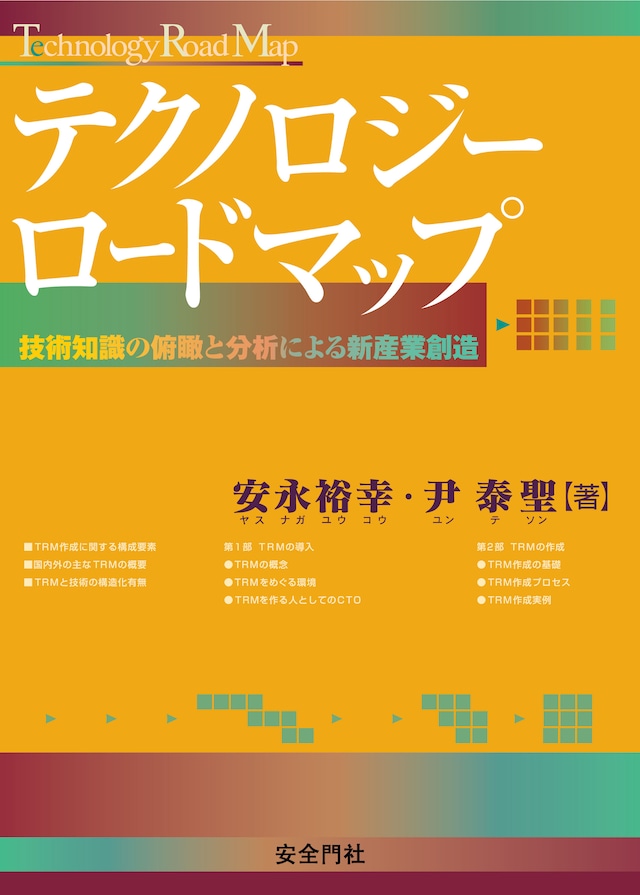
テクノロジー・ロードマップ―技術知識の俯瞰と分析による新産業創造
¥2,984
テクノロジー・ロードマップ―技術知識の俯瞰と分析による新産業創造 安永 裕幸 (著), 尹 泰聖 (著) ISBN(or ASIN): B07R1PCV3Z(印刷版のISBN-13: 978-4902444025) 頁数:214 形式:電子版PDF 発行日:2019年4月15日 (印刷版初版発行:2006年3月27日) 定価:本体2,713円+税 出版: 安全門社 [なかみをプレビュー] https://play.google.com/books/reader?id=Uy2UDwAAQBAJ&hl=ja&pg=GBS.PA18 「TRM(テクノロジー・ロードマップ)」の電子版がついに登場! 「TRM(テクノロジー・ロードマップ)」の印刷版が絶版となりましたが、再販売に関するお問い合わせが多かったため、このたび電子版を発行しました。 本書は、 TRM(テクノロジー・ロードマップ)に関する誕生背景から、理論、さまざまな分野への適用事例まで紹介している。本書の作成には、多方面の人々との意見交換から得たヒントやTRMへの期待までが参考になっている。これらの人々が属する分野は多方面であり、半導体、化学、金属、機械、自動車、エネルギー、環境、プラントはその一部である。また、これらの人々の肩書きは企業の研究企画担当者、各大学の関連研究者、知識工学、俯瞰工学、技術経営の研究開発者まで多様である。意見交換過程では、海外の専門家とも直接面談し、様々な課題を議論した。これらの過程で感じたのは、僭越ながら次のようなことである。 1 TRMという概念自体は多くの関係者が認識し、かなりの企業で作っている。我々が調べた範囲では、企業のTRMは3年~5年をターゲットにしているのが多い。しかし、企業の研究開発戦略にTRMが十分活用できているかに関しては確実ではない。 2 TRMは科学的アプローチを指向している。そのため、多くのサブシステムから構成されるシステム製品の研究開発には有効な内容がいくつも提案されている。しかし、広範な用途を有する材料分野、製品イメージが確定しにくい先端分野、現行の経済メカニズム下では市場が見えにくい分野に関しては、アプローチが十分とは言えない。 3 新産業創出のためには、大胆な異分野融合によって技術のフロンティアを拓くべきである。いっそのこと、TRMあるいはTRMの作成過程を通じて、融合の仕掛けをしていくべきと期待している関係者が多い。 本書を一言で表現するならば、「TRMとは、技術を構造化し可視化する、研究開発マネジメントの科学的アプローチとそのツールである」ということを説明しているものである。そのため、TRMの策定と活用に関連する話題を集めている。 これまでのTRMは、どうしても「既に構造化された」技術体系を基に策定され、活用されることによってその有効性を示してきた。しかし、今後日本が国際競争の中で技術の力によって勝ち抜いていくためには、「未だ構造化されていない」技術分野を、TRMあるいはその作成過程によって構造化しながら、技術戦略、事業戦略、国家戦略の統合を図るアプローチが必要であろう。 著者略歴 安永 裕幸(ヤスナガ ユウコウ) 1962年生まれ。1986年、東京大学工学部修士課程(資源開発工学)修了。その後通商産業省(当時)に入省。宇宙開発(資源リモートセンシング、無重力環境利用実験)プロジェクトのマネジメントや半導体研究開発プロジェクト立案などの政策に携わるとともに、国際石油情勢分析、日米半導体協定交渉、アジア経済危機対策、電子商取引の著者コンフィデンス対策などの国際分野の行政分野にも関わる。NEDO技術開発機構での研究開発プロジェクト・マネジメントを経験した後、2005年9月より経済産業省で研究開発課長として技術行政を担当。専門分野は、研究開発マネジメントと技術ロードマップ、技術の構造化とアーキテクチャ論、電子デバイス産業の競争力分析など。(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです) 尹 泰聖(ユン テソン) 1961年生まれ。東京大学工学系研究科にて博士号(工学)を取得後、東京工業大学助手と経済産業研究所客員研究員を経て東京大学工学部総合研究機構助手、東京理科大学経営工学科講師を歴任。現在、東京大学工学部研究員。「国際CAD/CAMジャーナル」編集委員。科学技術知識プロバイダーとして、活用可能な科学技術知識の流通・活性化を手掛ける(株)オープンナレッジの代表取締役でもある。世界的な人名辞書「Marquis Who’s Who in Science and Engineering」に紹介されている。専門分野は、知識ビジネス論と生産情報工学。知識の構造化・再構築・流通・活性化からなる連続サイクルを知識ビジネスの本質として捉え、その実体を研究開発している。(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
-

知識の構造化・講演 | Lecture on Structuring Knowledge
¥1,854
知識の構造化・講演 著者:小宮山 宏(こみやま ひろし、Hiroshi KOMIYAMA ) 出版: 安全門社 ISBN(or ASIN):B07QXCSTZF (印刷版のISBN:978-4-902444-62-9) 頁数:254 形式:電子版PDF 発行日:2019年4月15日 (印刷版初版発行:2007年12 月16 日) 定価:本体1,685円+税 [なかみをプレビュー] https://play.google.com/store/books/details?id=yieUDwAAQBAJ 内容紹介 「知識の構造化・講演」の電子版がついに登場! 「知識の構造化・講演」が絶版となりましたが、再販売に関するお問い合わせが多かったため、電子版を発行しました。 「知識の構造化・講演」は、「知識の構造化」の講演バージョンです。 「知識の構造化」をもっとわかりやすく!さらに新しく! 日本最高レベルの知識人・東大総長小宮山氏の最新刊!! 天然資源に乏しく国土も狭い日本が、なぜ世界第二位の経済活動を行えるのか? 日本の技術は、世界のどのレベルに位置している? エネルギー問題、環境問題、医療問題、温暖化問題、少子高齢化問題・・山積みの課題を東大総長はどう解く? 細分化された知識の山、これらを把握し活用するには何から始めるべき? 五十年後の日本と世界の未来は明るい? 講演バージョンでよりわかりやすく、さらに新しい情報が追加されて読み応えも十分! 東大総長小宮山宏氏が、専門家ではなく一般の人に提唱する「知識の構造化」、充実の内容をわかりやすく説いた一冊。 日本の未来と世界の知識レベルがこの一冊に詰まっています。 [著者紹介] 小宮山 宏 (こみやま ひろし, Hiroshi KOMIYAMA) 東京大学総長 1944年栃木県生まれ。1967年東京大学工学部化学工学科卒業。 1973 ~ 74年カリフォルニア大学(デービス校)のフェロー。1988年東京大学教授、 2000年同大学大学院工学系研究科長・工学部長、2003年同大学副学長、 2005年以来現職。 著書に、『課題先進国』(中央公論新社)、『東大のこと、教えます』(プレジデント社)、『知識の構造化』(オープンナレッジ)、『地球持続の技術』(岩波新書)、『地球温暖化問題に答える』(東京大学出版会)などがある。 専門は、知識の構造化、化学システム工学、地球環境工学。 総長就任以来、「東京大学アクションプラン」を公表して改革を進め、現代のリベラルアーツの構築、学術統合化を進めている。 (本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです。)
-

知識の構造化 | Structuring Knowledge
¥2,984
知識の構造化 著者:小宮山 宏(こみやま ひろし、Hiroshi KOMIYAMA ) 出版: 安全門社 ISBN(or ASIN):B07QZP2CFW (印刷版のISBN: 978-4-902444-03-2) 頁数:222 形式:電子版PDF 発行日:2019年4月15日 (印刷版初版発行:2004年12月24日) 定価:本体2,713円+税 [なかみをプレビュー] https://play.google.com/store/books/details?id=ntqUDwAAQBAJ 『知識の構造化』の電子版がついに登場! 『知識の構造化』が絶版となりましたが、再販売に関するお問い合わせが多かったため、このたび電子版を発行しました。 元東大総長 小宮山宏氏による提言! 20世紀、知識は爆発的に膨張した。 21世紀、膨張した知識をどうする? 切り札は「知識の構造化」!! 20世紀、科学的方法論の確立によって人類の持つ知識は飛躍的に増大しました。しかし、知識は単なる情報(データ)として死蔵されているだけでは価値を生み出しません。知識に生命を与え、十分に活用できる状態にし、その真価を発揮させること。これこそが「知識の構造化」の目指す本質であり、21世紀の人類の課題です。ITの進歩により、その実現への道具立ても充実してきました。 まず、本書第一部では、20年来知識の問題を熟考し続けてきた筆者により、この知識をめぐる困難な現状と、その解決策たる「知識の構造化」の概念が語られます。 さらに、第二部では、具体的な日本企業数社の知識戦略を俎上に載せ、詳細な分析、評価が加えられています。わが国の知識経営はどこまで進行しているのか?企業人のみならず、知識の問題を考える全ての現代人にとって極めて興味深い注目の書と言えます。 [目次] 第1部 「知識の構造化」の概念 第1章 知識の困難な現状 第2章 知識環境の理解 第3章 知識の構造化の提案 第4章 知識の構造化の利用 第5章 知識の構造化の要素 第6章 知識の構造化の評価基準 第2部 「知識の構造化」の実現 第7章 知識の構造化を目指すプロジェクト例 第8章 企業における知識の取り扱いの現状と評価例 日立製作所、三菱重工、住友化学、NEC、花王、日揮、トヨタ、 三井物産、三井住友銀行など。 [著者] 小宮山 宏(こみやま ひろし) 1967年3月、東京大学工学部化学工学科卒業。 1988年7月、東京大学工学部教授。 2000年4月、東京大学大学院工学系研究科長、工学部長。 2003年4月、東京大学副学長、東京大学附属図書館長。 2005年4月、国立大学法人東京大学総長(第28代)(2009年3月まで) 〈専門分野〉 化学システム工学、地球環境学、知識の構造化。 2009年4月、三菱総合研究所理事長に就任 (本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです。)